准教授 酒井康弘
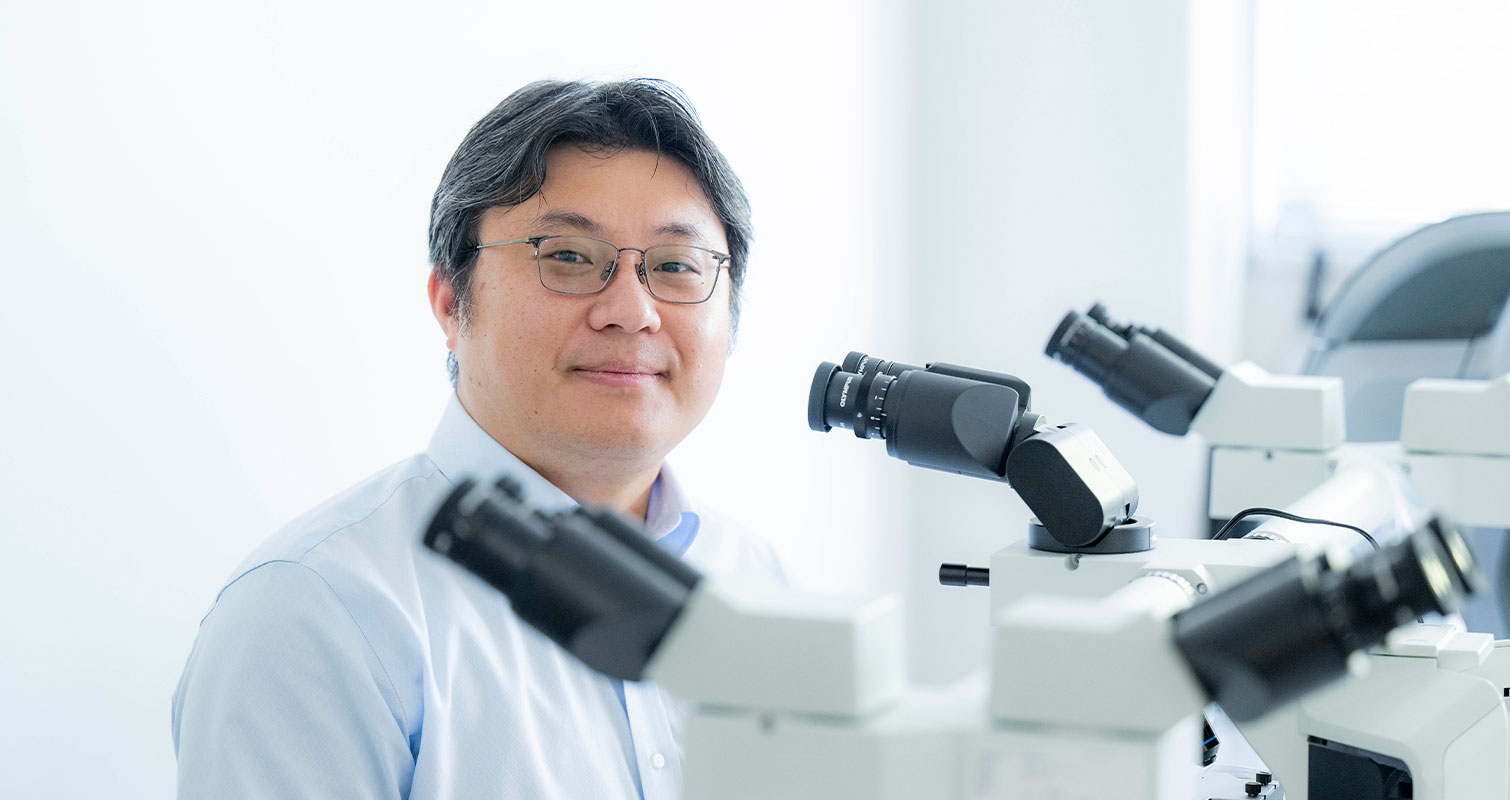
ナノセイバーと病理医
NHK『天才てれびくん』内で放送されていたアニメ『救命戦士ナノセイバー』をご存じでしょうか。医師が体内へ小さくなって入り、病気を見つけて治療する――そんな近未来の設定でありながら、実在する病気や病理学的な視点を土台に物語が展開していました。
子どもだった私は、組織や細胞の傷害が症状・徴候へと結びついていくダイナミズムに心をつかまれ、「すごい!こんな医者になりたい!」と感動したのがすべての始まりでした。やがて医学生となり、病理学という学問に出会ったとき「これこそナノセイバーだ!」と胸が高鳴り(さすがに“ナノ”ではなく“ミクロ”の世界ですが)、卒業後は迷わず病理学の道に飛び込みました。
子どもだった私は、組織や細胞の傷害が症状・徴候へと結びついていくダイナミズムに心をつかまれ、「すごい!こんな医者になりたい!」と感動したのがすべての始まりでした。やがて医学生となり、病理学という学問に出会ったとき「これこそナノセイバーだ!」と胸が高鳴り(さすがに“ナノ”ではなく“ミクロ”の世界ですが)、卒業後は迷わず病理学の道に飛び込みました。
がん研究に踏み出し、転写共役型DNA傷害の解明を進める
大学院生の頃、何人もの先生から「がん研究は正常から外れるあらゆる道筋を扱う学問だ。だから終わりの見えない迷宮に感じるだろう」と諭されました。それでも私は、その迷宮にこそ人間の病の本質が潜んでいると感じ、むしろ飛び込む決心を固めました。ご縁が重なり、転写共役型DNA傷害を研究されている先生と一緒に仕事をする機会に恵まれ、論文執筆にも携わることができました。
転写共役型DNA傷害とは、DNAからRNAへの転写の進行に伴って生じるDNA損傷の総称です。転写の最中、新生RNAが鋳型DNAへ「逆戻り」して二本鎖をつくり、相補鎖の一本鎖DNAを押しのけた三本鎖様構造――すなわちRループが形成されます。Rループはプロモーターやターミネーターなどで生理的にも生じ、遺伝子発現の微調整や転写終結に役立つことがありますが、過剰かつ持続的に生じると複製フォークの障害物となり、ゲノム不安定性の引き金になります。Rループが高頻度に形成される領域では二本鎖切断や染色体脆弱性が増し、Rループそのものが転写の早期終結やクロマチン構造変化を誘導することも示されています。
転写共役型DNA傷害とは、DNAからRNAへの転写の進行に伴って生じるDNA損傷の総称です。転写の最中、新生RNAが鋳型DNAへ「逆戻り」して二本鎖をつくり、相補鎖の一本鎖DNAを押しのけた三本鎖様構造――すなわちRループが形成されます。Rループはプロモーターやターミネーターなどで生理的にも生じ、遺伝子発現の微調整や転写終結に役立つことがありますが、過剰かつ持続的に生じると複製フォークの障害物となり、ゲノム不安定性の引き金になります。Rループが高頻度に形成される領域では二本鎖切断や染色体脆弱性が増し、Rループそのものが転写の早期終結やクロマチン構造変化を誘導することも示されています。
Rループ制御とDNA傷害の関係を明らかにし、病気のメカニズムに迫る
興味深いのは、この仕組みが「善悪二面性」をもつ点です。B細胞の免疫グロブリン遺伝子では、Rループがクラススイッチ組換えや体細胞超変異の舞台装置となり、抗体の親和性成熟に貢献します。
一方で、がん遺伝子やがん抑制遺伝子でRループ制御が破綻すれば、腫瘍化のドライバーとして働きかねません。したがって、細胞にはRループを作らせない仕組みがあります。THO/TREXやTREX2などのmRNP形成・輸送系やトポイソメラーゼが、転写と同時にRNAをタンパク質で包み、ねじれ応力を逃がして「逆戻り」を抑えます。この抑制が間に合わないまま細胞が複製期に入ると、転写‐複製の正面衝突が二本鎖切断へ発展し、BRCA1/2を中核とする相同組換えやファンコニ経路などの修復機構が総動員されますが、それでもDNA損傷が残ることがあります。がん細胞ではRループの偏在によって慢性的な炎症とゲノム不安定性が進行します。
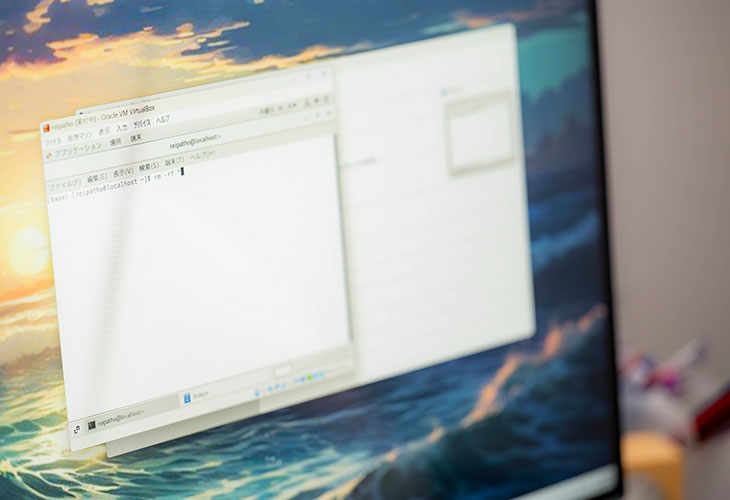
私たちはその実像に、病理医の視点から迫っています。研究対象の分子は免疫・神経・修復にまたがり、多彩な生命現象との接点が見えてきます。
形態×分子×臨床をつなぎ、診断と治療選択に活かす
浜松医科大学腫瘍病理学講座のがん研究は、形態(顕微鏡)と分子(遺伝子・シグナル)をつなぎ、臨床へと橋渡しすることを軸に進めています。
たとえば、私はDNA損傷応答と腫瘍の生物学的依存性や感受性に焦点を当て、転写共役型DNA傷害やRループの制御破綻がもたらす病態の特徴とその分布を可視化し、将来的なコンパニオン診断の実装を視野に入れています。病理像、オミックス、機能解析を立体的に組み合わせることで、DNA修復経路の偏りや依存性を可視化し、治療選択に資する知見へとつなげていきます。
研究と臨床を往還させるために、近隣病院や多職種と連携して、デジタル病理やAI支援診断の導入も進めています。
たとえば、私はDNA損傷応答と腫瘍の生物学的依存性や感受性に焦点を当て、転写共役型DNA傷害やRループの制御破綻がもたらす病態の特徴とその分布を可視化し、将来的なコンパニオン診断の実装を視野に入れています。病理像、オミックス、機能解析を立体的に組み合わせることで、DNA修復経路の偏りや依存性を可視化し、治療選択に資する知見へとつなげていきます。
研究と臨床を往還させるために、近隣病院や多職種と連携して、デジタル病理やAI支援診断の導入も進めています。
他にも、私たちの教室員がさまざまな研究成果を挙げています。たとえば、胸部悪性腫瘍の鑑別に、podoplaninの免疫組織化学とNanoSuitを用いた相関光–電子顕微鏡法(CLEM)を組み合わせ、同一標本で光学像と超微形態を対応づけることで、上皮様悪性胸膜中皮腫に特徴的な所見を確かめながら非小細胞肺癌と見分ける現場実装の手順を提示しました。
希少がんである小腸腺癌では、包括的免疫表現型と多領域ゲノム解析を統合し、従来型の大腸癌とは異なる分化像と進化動態を示すサブタイプを明確化しました。いずれも、形態と分子を往復しながら臨床判断に直結させる、私たちの研究の進め方を体現しています。
希少がんである小腸腺癌では、包括的免疫表現型と多領域ゲノム解析を統合し、従来型の大腸癌とは異なる分化像と進化動態を示すサブタイプを明確化しました。いずれも、形態と分子を往復しながら臨床判断に直結させる、私たちの研究の進め方を体現しています。

さらに、腫瘍の脆弱性に迫る基盤研究として、非小細胞肺癌で中心体形成因子STILの制御破綻が中心体過剰と染色体不安定性に結びつく仕組みを示し、層別化や治療標的の可能性を示唆しました。国際共同研究として、アフリカ地域の大腸癌コホートでTP53変異プロファイルとCMS亜型の偏りを明らかにし、現地医療に根差した分子病理の道筋を提示しました。
これらの知見を結び合わせ、形態×分子×臨床の橋渡しを一段と加速させていきます。
これらの知見を結び合わせ、形態×分子×臨床の橋渡しを一段と加速させていきます。
私たちの強みと学べること
私たちの教室の強みは、マルチモーダル解析を運用している点にあります。H&E染色や特殊染色、免疫組織化学、デジタル画像、遺伝子・転写・エピゲノムの情報を一体として扱い、症例から現れた手がかりを分子の仮説へ、分子の仮説をふたたび形態の検証へと循環させます。普段の病理診断で生じる疑問に正面から向き合い、その課題を研究の問いに落とし込み、紙の上の理論ではなく臨床に返る知見を積み上げてきました。臨床、分子生物学、情報科学の研究者とフラットに協業し、プロジェクトの初動から成果の発信までを一貫して進められる点も、私たちの教室の特徴です。特に大学院生には、標本作製からデジタル病理、免疫染色や分子実験、データ解析、論文執筆・学会発表に至るまで、実際に手を動かし、考え、書くという研究の作法を最初から最後まで体得してもらえるようにしています。
一緒に腫瘍病理学をやりましょう

私たちは、病理医に興味のある医学部生・研修医や、臨床科の大学院生、コメディカル、そしてデータサイエンスやエンジニアリングに関心のある皆さんを幅広く歓迎します。がんは確かに「終わりの見えない迷宮」かもしれません。しかし腫瘍病理学は、その地図を描き、抜け道を見つけ、次の一手を指し示す学問です。
顕微鏡の向こうに広がる分子の風景を読み解き、患者さんの治療へと橋渡しする――この知的な冒険に、ぜひ加わってください。
見学や相談はいつでもお待ちしています。あなたの最初の一歩が、新しい診断や治療の扉を開くかもしれません。
顕微鏡の向こうに広がる分子の風景を読み解き、患者さんの治療へと橋渡しする――この知的な冒険に、ぜひ加わってください。
見学や相談はいつでもお待ちしています。あなたの最初の一歩が、新しい診断や治療の扉を開くかもしれません。

