石川励先生

これは主観ですが、病理を志すものの半分くらいは漠然と研究にも興味があると感じています。病理は臨床と研究のどちらにも属しており、日常業務の中で自然と研究に必須の知識や技術をトレーニングできます。各科から貴重な症例が集まりやすく、生検や手術で摘出された検体へのアクセスがよいのも特徴です。
症例が蓄積されると、学会で発表をする機会が多くなります。臨床の先生が論文としてまとめ、名前を入れてくださることもあります。病理専門医の研修期間は3年ですが、それだけあれば上記のことは一通り経験でき、専門医も苦労なく取得できます。
市中病院ではどうしてもcommon diseaseが多いため、大学病院など比較的大規模な病院での研修をおすすめします。給料は安いかもしれませんが。
症例が蓄積されると、学会で発表をする機会が多くなります。臨床の先生が論文としてまとめ、名前を入れてくださることもあります。病理専門医の研修期間は3年ですが、それだけあれば上記のことは一通り経験でき、専門医も苦労なく取得できます。
市中病院ではどうしてもcommon diseaseが多いため、大学病院など比較的大規模な病院での研修をおすすめします。給料は安いかもしれませんが。
専門医を取得すると、一通りの目標達成といえます。上記の通り、病理は先天的にも後天的にも研究のインスピレーションを受けやすく、そのハードルも他科ほどは高くありません。研究で必須の病理学的な形態像、免疫染色の評価や抗体選び、多少の遺伝子学的な知識が身についていることは、病理専門医機構が保証しています。私も専門医取得と同時期に大学院へ入学しましたが、それは自然なことだと思います。
「何となく研究は難しそう」というイメージをお持ちの方が多いかと思いますが、端的なことを申しますと、研究テーマや目標によります。本学の要綱には、博士論文について「査読付きの英文原著論文であり、筆頭著者であること」「論文がアクセプトされていること」以外の条件はありません。
「何となく研究は難しそう」というイメージをお持ちの方が多いかと思いますが、端的なことを申しますと、研究テーマや目標によります。本学の要綱には、博士論文について「査読付きの英文原著論文であり、筆頭著者であること」「論文がアクセプトされていること」以外の条件はありません。
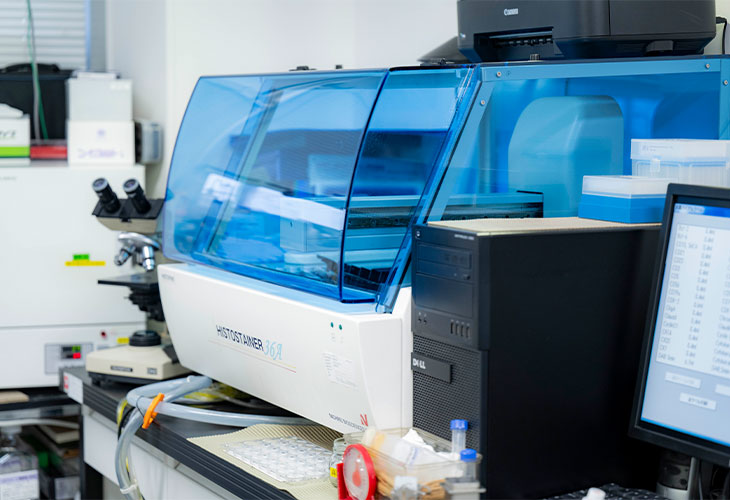
この条件がさらに緩い大学もあり、多くの学生が学内誌で卒業していた例もあります。由々しき事だと思いますが、そういう意味では過度に身構えなくていいと思います。研究スタイルは講座によって異なり、テーマや目標、サンプルやプロトコルが全て与えられるところもあれば、全て自分で考えて行動するところもあります。後者の方が大変ですが、やりがいや将来性も大きいです。私たちの講座ではどちらも可能です。
最後に、博士を取得することのメリットを述べたいと思います。せっかく大きな学会に参加しても、内容が半分も理解できないという経験はありませんか?それは知識が不足しているだけでなく、そもそも研究者としての思考が不足していることが大きな原因です。1つのことを証明するには遺伝子、組織、生きた細胞やマウスなど複数の実験系で観察しなくてはなりません。サンプルの作製や品質管理など、「実験の実験」も重要です。この感覚が研究をしないとわかりません。系統立てて説明してくれているのに、全て独立した結果に見えます。証明が不十分なのに証明されていると錯覚することもあります。私の体感では、得られる知識が1:10くらい違います。
医師としてのキャリアは生涯続きます。専門医取得後、何となく次の目標が欲しくなっていませんか?そのときが研究の始めどきです。
医師としてのキャリアは生涯続きます。専門医取得後、何となく次の目標が欲しくなっていませんか?そのときが研究の始めどきです。

